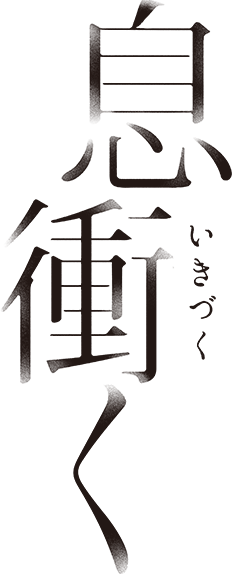各界からの
コメント

酒井善三 / Zenzo Sakai / 映画監督
狭義の宗教にとどまらず、生きていく上での信仰、
この空虚な世界を「生きるモチベーション」を見つけられずにもがく人々。
一つの大きな普遍的主題が通底している。
俯瞰せず、目高の高さの群像劇であるがゆえに、複雑さが複雑さのままに、
残酷な現実の曖昧さ、豊かさが豊かさのままに映っている。
これは自分の物語でもあるのだ。
きっと、そのように、誰の物語でもある。
宮台真司 / Miyadai Shinji / 社会学者
政教分離の意味は二つある。
第一:政治が特定宗教を贔屓しないこと。
第二:宗教が「信者なら××せよ」と政治動員しないこと。
後者が難しい。価値観に基づく政治参加は大切で、その価値観は宗教に由来してよい。
だが「信者なら××せよ」は範囲を超えるのだ。どう超えるのかを一言で述べづらい。
『息衝く』はその難しさに「社会」ならぬ「実存」の側から切り込む。宗教二世なら覚えがあろうが、
「信者なら××せよ」という命令に従うことと、宗教的信念に従うことの、微妙かつ大きな違いは、
実存の側から見て初めて判るのである。
佐藤良祐 / Ryosuke Sato / 映画監督
3.11以降、寄りかかる信仰を無くした者たちが、それでも誰かを求めるあまり、もがき、隔たりをつくりながら彷徨うこの物語は、スクリーンの窓を通して、僕たちの暮らしと繋がっている。
僕らのパーソナルな歴史と深く繋がり、その息苦しさは自分自身の息苦しさに似てるのではないかと錯覚を覚えながら、彼ら、彼女らの未来を見守った。 高度経済成長期に生まれ、バブル崩壊の流れによって上場企業に勤めていた父が左遷、小学校の時から青春期にかけて7年間の単身赴任となった。父が単身赴任から戻った時、平日でも昼過ぎには家にいて、玄関先でゴルフの素振りをしていたのをよく覚えている。 その後に両親は離婚した。
僕の母も、おそらくは新興宗教にハマり、家には空から力が降ってくるというシールや、遠出するたびに、どこかの平家に連れていかれ、仏像のようなものにお祈りをした思い出がある。
90年代のどこかでポケットに入れて出すこともなかった自分のパーソナルな物語は、この映画の物語のどこかと繋がり、今の自分に迫ってきた。親世代から受け継がれた、「豊かな暮らしを願う信仰」と、「そんな事は今更わかってる事だろ」というある種の諦めの狭間で、僕たちは何を願い、祈り、子供達に伝えるのか。
物語の終盤、森山の滑稽極まりない変わり果てた姿が、清々しい希望の断片のように思えてならなかった。 そして、森山の元で一夜を過ごした朝、台所にいる慈の周りを則夫、大和、森山がそれぞれフレームイン、アウトするシーン、ある家族の朝のワンシーンのようで、なぜかすごく感動した。
久保田桂子 / Keiko Kubota / 映像作家
自分の感情の無意味さと沢山の時間の浪費、特に震災以後の社会に対する無力さ、流されていく感じの中で、周囲と自分を肯定する、
なんとかそこで踏ん張ろうとするのは、自分にとっては苦しい。
かつて自分が目にした大事なひとの信仰の施設。そこを訪ねた時の気持ち、結局形は違うだけで、そこにも日常と寂しさがあるだけなんだ、
と思ったこと、行き場のない人びとのセーフティーネットとしての宗教組織を、肯定する気持ちと反発なども思い出し、映画を観ている間、細部の危うさとどぎつさに時々戸惑ったりもしたが、なにより作品の全体を貫く、目に見えない気迫のようなものにあてられて呆然としてしまった。
常に所在なさげな則夫の佇まいや、他人(母、男性、主人公)の欲望を投影させられた儚い像のような慈に少しの息苦しさを感じるのは、
彼らのような顔を自分は知っているような気がするからだ。そう思いながら、同時に、主人公は今まで自分の時間を生きたことがどのくらいあるのだろう、とふと気になった。
彼らがその後、自分の人生の時間を作り出せるのか、また別の時間の中で流されていくのか。
とにかく、まだまだ続くんだ、と、会場を出た帰り道、さっきスクリーンの中で見たような風景の中歩きながらずっと考えていた。
西岡研介 / Kensuke Nishioka / ノンフィクションライター
新聞、雑誌記者時代、作品のモデルとなった宗教団体をはじめ、いくつかの新興宗教を取材してきた。
時には政治との絡みで、あるいは事件との関係から。ただ、その時に私が見ていたのは、あくまで信者の「集団」であって、「個」ではなかった。
当たり前の話だが、結果的に集団を形づくる個は、各々に生い立ちも違えば、それぞれに異なった苦悩や葛藤、諦念を抱えている。
また、個々によって、集団と保つ距離も違えば、考え方も違う。そして、これも至極当然のことなのだが、それらは歳月を経るごとに変わっていくし、さらには身近で、あるいは社会で起こった様々な出来事に触れることによって、変化もしていく。
しかし、私はそれら「集団」の中の「個」に目を向けようとしなかった。いや、無意識のうちに避けてきた。
なぜなら私にとってそれらは、集団を描く上で正直、厄介で、邪魔な存在だったから。
だが、木村文洋の視点は私のそれとは真逆だ。あくまでそれぞれの個に照射することによって、それらが形成する集団、さらには社会の「今」を浮き上がらせる。
そういう意味で木村の紡いだ本作品は、フィクションの体裁をとった「ドキュメンタリー」と言えるのではないか。
木村友祐 / Yusuke Kimura / 小説家
我が身の幸福を願う以上に、他者の幸福のほうをより多く願う。
そのためにもがく若者たち。
また、そのためにこの映画は、真正面から「政治」を題材とした。
『息衝く』を観ながら、おれはこんな小説が書きたかったんだと全身がざわつき、高ぶり、軽い嫉妬をおぼえていた。
息ができない現代日本の空気感を生々しくとらえながら、それでも〝まっとうさ〟を希求する本作の純真なたたずまいに、胸打たれずにはいられない。
島田裕巳 / Hiromi Shimada / 宗教学者
親が新宗教の信者というのは、子どもにとっては厄介なことである。
だが、そうしたケースは少なくない。
さらに厄介なのは、両親が信者ではなく、片方だけが信仰していたり、信仰の違いで離別してしまったときだ。
子どもは生涯にわたって、信仰の問題に直面し、悩まなければならなくなる。
親と同じ信仰を持つのか、信仰ということ自体を徹底的に排除するのか。
ずっと冷静ではいられない。おまけに、経験がない人間には、この苦悩は理解してもらえない。
親と子と信仰。これは、三位一体の関係にある。そんな関係が成立してしまうのも、その背景には貧しさがあり、社会の矛盾があるからである。
社会は冷酷で、その矛盾を弱者に押し付けてくる。弱者は居場所を失って、新宗教に逃げ場を求める。
この映画に登場する「南無妙法蓮華経」の題目は、そして、題目を唱え続ける人々が作った組織は、果たして、そうした矛盾から人を救い出してくれるのだろうか。
それは、映画が提起する重要な課題だ。
瀬々敬久 / Takahisa Zeze / 映画監督
不在のヒーローにまつわる政治と闘争と宗教についての物語と流民の男女のラブストーリーがうまく融合されてないんじゃないかと最初は見ていたが、最終的にはそういうことはどうでも良くなった。
うまいとかヘタとか、よく出来てるとか失敗とか、そういうことは一切もはや関係なく、木村文洋の“うめき”みたいなものを感じた。それは今までになく感じた。
『へばの』の西山真来がラスト近く青森の光景の中に突如登場した瞬間、思わず落涙。
作品を股にかけ、人生を賭して、自分の主題を追求し続ける映画監督がまさにここにいる。そう確信した。
廣瀬純 / Jun Hirose / 批評家
『へばの』ではロングショット、『愛のゆくえ(仮)』ではミディアムショットがそれぞれ作品全体を支配するショット形態となっていた。前者では、六ヶ所村の風景のなかにつねにすでに投企された状態において若い男女を捉えること、後者では、長い逃亡潜伏生活を脱し外部へとおのれを再び開いていこうとする過程において恋人たちを捉えることが、それぞれ問題になっていたからだ。
『へばの』とディプティカをなす『息衝く』ではクロースアップが支配的ショット形態となっている。六ヶ所村のそれに対するオルタナティヴとして東京に見出されたロングショット、その下で青年たちが共に生き続けていくはずだったもうひとつのパースペクティヴは、トラヴェリングによって回復不能な過去へと押し流され、青年たちは個々に別々の狭いフレームのなかに収まることを余儀なくされている。
しかしどのクロースアップも完全には閉ざされていない。
それぞれの深奥で、ロングショットを希求する情熱がなおも息衝いているからだ。
木村文洋のクロースアップには、まだ存在しない大いなるロングショットへと再び踏み出される新たな一歩としてのミディアムショットのその萌芽が胚胎されているのだ。
福間健二 / Kenji Fukuma / 詩人・映画監督
130分、心を揺さぶられた。
そして映画をめぐる根本の問いをよみがえらせていた。
なぜ映画を作るのか。
映画は何ができるのか。
自分の問題と社会の問題は別のことではなく、生きることと映画を作ることも別のことではない。
『息衝く』の木村文洋は、そうであるためにはどうすればいいかを問いつづけながら、私たちの未来への視界を塞ごうとするものに全力でぶつかっている。
岡藤真依 / Mai Okafuji / 漫画家・イラストレーター
あなたはそれでいいのですか?自分だけが幸せでいいのですか?
息苦しくなるほど沢山 問いを投げかけられ、映画についてずっと考えてしまう。
この作品を観て、私の中の何かが変わったような気がしました。

先崎彰容 / Akinaka Senzaki / 日本大学教授
あの震災以降、どれだけの言葉が紡がれたのだろうか。
まず国を批判する言葉があった。
「再稼働反対!」と絶叫する言葉もあった。
国会前は騒然となり、高らかな声が夜の街灯を震わし、また青空に吸い込まれる日もあった。
だが、私の心を動かす言葉は何一つなかった。
なぜか。
全ての言葉が、私の生活の水準線より一ミリ高かったからだ。
「社会問題を考える」とは、今、踏みしめている生活を離れてはあり得ない。
私という、このかけがえのない、しかしどこにでもいる人間の日常の軌跡から外れた「大問題」など存在しない。
そうだ。
国家のあり方を考えるのに、詩人や英雄はいらない。
僕たちはもっと、散文的であらねばならぬ。
「息衝く」は、言葉ではない。
映像だ。
映像によって人の心を喚起し、考えさせ、言葉を生みだす力を与える。
もう十分に見るに値するではないか。
どこまでも暗い映像のその先に、イデオロギーの左右などぶち抜いた衝撃が襲ってくる。
市井を生きる者たちが、誰にも気づかれることなく抱えている不安・理想・挫折――
掛け値なしに、この作品は、私たちに寄り添っている。
信田さよ子 / Sayoko Nobuta / 臨床心理士
宗教、カルト、原発、家族といったテーマがこれでもかと詰め込まれている欲張りな映画である。
盆栽のように小さくまとまったり暴力を垂れ流す映画が多いなかで、そのスケールの大きさに久々に感動させられた。
七尾旅人 / Tabito Nanao / シンガーソングライター
偶然見かけた「息衝く」のインフォメーション。
けして見逃してはならない直感があった。
2006年、六ヶ所村で生きる人々を描いた「へばの」から10年余に及ぶ執念で製作されたというこの続編が、 政党をも有する日本最大の日蓮系新宗教の圏内で生きる若者たちの群像劇であることに驚かされた。
誰も切り込めなかったテーマ、前例のない作品だ。
安易な否定/肯定に偏ることなく、強い当事者性を維持したまま、信仰と政治のリアルな葛藤が映し出される。
抗いきれぬ大きなうねりの中で、個々の登場人物が抱えるストラグルや願いもまた、等しい質量で描写される。
ここに映り込んだ人々を、あなたは、愛せるだろうか、それとも、嫌悪するだろうか。
これほど無防備で、必死で、不器用で、頼りなく、ちっぽけで、壮大で、勇敢な映画は、観たことがない。