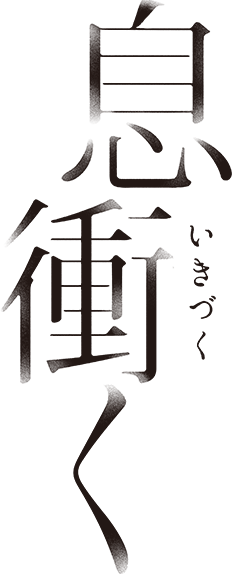上映日誌

【批評】「依法不依人」について ―『息衝く』における宗教と政治 Resurrections vol.1-最終回

2018年批評誌『Resurrections vol.1』から最終回、鎌田 哲哉さん(批評家)と本作監督・木村との対談を掲載いたします。
「依法不依人」について ―『息衝く』における宗教と政治
鎌田 哲哉(批評家)× 木村 文洋(『息衝く』監督)
鎌田 哲哉(以下、敬称略)
「鎌田です。『息衝く』がようやく完成し、色々な上映主体や映画館によって、繰り返し上映されている。変な人気や、流行にならない代りに、僕達観客を少しずつ集めて、確実に深い波動をもたらしている。そのことがうれしいです。本当におめでとうございます。
この映画ができる過程で、僕は木村さんとひんぱんに話したわけではありません。お互い時間がなくて、しばらく音信不通になっていた時もあったんじゃないかな。ただ、『息衝く』と引き換えに、木村さんはすごく傷ついた。進んで大きな犠牲を払ってきたし、逆に他人を傷つけ、桑原さん達に犠牲を払わせたというか、多大な迷惑をかけた時もあったと思いますが(笑)、最後の方は一人になってでも、強引に映画を完成させていた。そういう印象をずっと持っていました。何が言いたいかというと……木村さんの場合、最初に「実践」があるんです。自分ばかり見つめる、まず自分を変えます、実践はその後でやります、自分が変るまでは何もできません。そう言って「自分語り」を正当化する錯覚が、木村さんにはない。何かをやること、対象を変革することでしか、自分が変ることはありえない。物事の順番が、それ以外にないことをわかっている人の映画なんですね。
その上で、今日はこの映画の「傷」。つまり欠けている所、絶対的に足りない部分を具体的に批評したい。今、「傷」という言葉を使ったのには理由があって……僕は一月の後半に、渋谷の最後の試写会でこの作品を見ました。ただ、その日すぐ札幌に帰る予定があり、終った後でスタッフの皆さんと握手して、「すごくよかった。嘘は一つもない。傷が多い映画だけど、頭でわかったふりをした個所は全くない」とか何とか言って、ダッシュして空港に向いました。でも、木村さんにごまかしはきかない。岡山に戻った後、僕達の共通の友人から心配というか、忠告の電話があったんです。言葉通りでないですが、木村さんが何かの機会に、(鎌田さん、ちゃんと批評していたのかな)と言う意味の表現を、ぽつんと口にしたって。その友人はおしゃべりではない。まじめな、普段は口が固い人です。だから、木村さんの言葉のトーン、調子がよほど気になって連絡をくれたと思います。それで見破られたというか、木村さんに隠しごとはできない、と改めて思った。自分が「傷が多い」とうっかり口にした、その「傷」の内容を具体的に言葉にしないといけない。そうでないと、「お客さん」になれてももう「友人」でない。そう感じて、ためらった末ここに来ました。
では、何が『息衝く』に一番欠けているのか。この映画は「南無妙法蓮華経」というか、日蓮の教えに基く新興宗教を素材にしていますね。『よだかの星』に何度も言及しているように、そこには宮沢賢治の日蓮がある。「種子党」が国家や政治に積極的に関与する部分は、石原莞爾の日蓮を連想させないこともない。でも、肝心の日蓮そのもの。あるいは明治以後の言説に限って言うと、内村鑑三の日蓮がないように思います。日蓮が『開目抄』で言って、内村が『代表的日本人』でそれを日蓮の原理だと言い切った宗教的認識……何て言ったっけ(笑)。そうそう、「依法不依人(えほうふえにん)」。法に依りて人に依らず、という視点がこの映画には抜けている。少くとも、殆どそれが感じられなかったんです。
パンフレットのインタビューを読むと、木村監督は、日本人に信仰や政治は基本的には必要ない。そうだけど、「それでも、宗教は自分個人の人生、場所、心が疎外されているときに、必要とされるもの」だ、とも考えていて、映像自体がこの認識に立っている。確かに、それが宗教の一面だと思います。たとえば、明治期以後でキリスト教がどんな階層をとらえたかと言えば、佐幕派の……内村自身がそうですが、幕府の側にいて特権を失った武士の子弟であり、あるいは同化政策を強要された、アイヌ民族の子弟です。知里真志保は拒絶したけど、姉さんの幸恵やバチェラー八重子達は皆入信していて、則夫の母の入信もそれを連想させました。だから、木村さんの言う「疎外」された人達、「居場所のない」人達が宗教を必要とした。逆に宗教の方でも、そういう人に影響力を行使できたことは疑いない。でもね、僕は事柄をこのレベルだけで把握すべきでない、とも思う。それは結局、ニーチェの宗教批判……現世的な秩序に排除された人々の怨恨、リゼントメントが宗教の起動力である、という見方とほぼ同じですね。そういう見方は、何か宗教を矮小化している。宗教の思想構造を具体的に考えると、それと全く違う側面がみえてくると感じます。
内村は、日蓮の宗教の核心が「依法不依人」だと言った。「法」には依拠するが、「人」に依存してはならない。文殊や普賢のように、どんなに頭のいい人の言うことでも、文殊だから信じる、普賢だから信じるのはまちがっている。彼らの主張を承認するのは、あくまでそれらが「法」に照らして正当である限りのことで、それが日蓮の言う宗教です。原則的なものは正義や真理の普遍性にあり、直接的で感性的な人間関係は、あくまで二次的なものです。つまり、「超人的なカリスマが僕達を見捨てた」という問題設定自体が、日蓮にはないんですよ。『息衝く』にこういう視点があったら、則夫や大和の言動は相対化され、滑稽化されたし、映画自体が彼らのあり方にずっと批評的でいられたと思います。
もう一つ、『代表的日本人』との関係で言いたいのは……僕は今言ったことが、「世界の不在」とも関係あると思う。内村は、「依法不依人」に触れた個所でも他でも、日蓮のやったことはリフォーメーションなんだ、ルターの宗教改革と同じなんだ、と繰り返してるんです。マックス・ウェーバーとか丸山眞男も、鎌倉新仏教全体について似たようなことを言ってるけど、内村の考察はそれよりずっと早いし、明快です。それで、この視点が何を生みだすかと言えば、「日蓮の言動が「世界」につながっている」という感覚なんです。つながると言っても、世界が壁の向うにあって、日本が壁のこちらの特殊な境涯だ、という意味ではないですよ。むしろ壁自体がない。世界には「世界」しかなくて、日本もまたその一部でしかない。そこでは至る所で同じ問題が繰り返されている、という感覚です。全然関係ないけど、中上健次が若い頃、「世界はいつもギリシア悲劇を上演している」と言ってた。内村の日蓮を読むと、「世界はいつも宗教改革を繰り返している」って言いたくなる。日蓮を問うことがそのまま世界を問うことで、物を考える時に、自然にインターナショナリズムでやれるんです。それに比べると、木村さんの映画は「「家族」から始めて、「この国」を問う」という構造にはまりすぎていませんか。そこに「世界」が、少くとも「世界」への抜け穴や通路があるかな、って感じたんです。この点はどうですか。」
木村 文洋
「〝法に依って人に依らざれ〞ということ、そして鎌田さんが仰る、〝世界につながる〞ということは、私も読み知ってはいました。ただ、あくまで知識レベルの話、前提としてあってつくっていた、ということです。国柱会の田中智学、なにより井上日召はむしろ、〝宇宙につながる〞という言い方をします。そのためにまず法華経を唱える、としています。これは、個人と宇宙がつながって―その上で国家について考えられる、という思想です。戦時中にあって、その個と宇宙との間に天皇があり―日本こそが世界に統べる国にならなければないけない、という思想につながっていきました。
ただ卑近なことを言えば、私の人生に日蓮宗の宗教が接近してきたのは10代後半、1990年代後半でした。親族が日蓮系に入信し、そして私がそれから離れる形で、大学に入ってからの一年間、創価学会に所属しました。親から話されたことは、いま自身が抱えている隣人、家族との行き違いは―元を正せば先祖への思い・供養をすることから立ち直っていくこと。そして創価学会の友人から教えられたのは、日々の互いの切磋琢磨から、自己の日常の課題、この社会をよくしていく、という言葉であって―どちらかといえば私が生きていた現代において法華経や信仰は、近い日常のものに思えた、世界あるいは〝宇宙〞 につながる、という感覚は、現在の日蓮の付与のされ方として、現実感に乏しいものだったかもしれません。」
鎌田 哲哉
「うーん、僕は映画の感想しか言えないんで、どうも一般論で物を考えられないから。たとえば、ドストエフスキーの『悪霊』と木村さんの映画を比べるとするでしょ。『悪霊』にだって、スタヴローギンという絶対的なカリスマが出現して、主要な弟子三人、キリーロフやシャートフやピョートルは彼を崇拝して、結局そこから自立できない。昔、ジラールとか作田啓一が「モデル=ライヴァル」とか言って、そればかり分析していた。でもこの種の問題設定は、ドストエフスキーの世界の一部であって、全体ではないから。むしろスタヴローギン自体の問題。何者にも依拠依存しない人間が、しかもなお自らの言葉のひび割れに苦しむ問題の方が、作品にとって本質的なんです。『死の家の記録』だって、カリスマなど持たない、持ちようがない人間達が、「悪には悪の生き方がある」を押し通す時に何と衝突するか、を書いている。だから、カリスマとその弟子達が登場すること自体がおかしいとか、問題だと言うわけではないんです。それを逸脱する剰余、世界がそれだけに還元できない、という視線が、『息衝く』の制作者側にどこまであったのか、と思ったんです。
木村さんは今「宇宙」と言われたけど、それは遠くに飛びすぎというか(笑)、僕が言う「世界」と少し違う気がする。たとえば、「依法不依人」の「法」は、福沢諭吉の言葉で言えば「天」、「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」の「天」みたいなものです。その「法」や「天」が、僕の言う「世界」です。日蓮が「法」から「人には依存しない」原則を提示したように、福沢の場合も「天」から、「理のためにはアフリカの黒奴にも恐れ入り、道のためにはイギリス・アメリカの軍艦をも恐れず」という行動原則を引き出してくる。つまり、道理が通っている限り、あらゆるマイノリティ、少数派の意見を心から尊重しないといけないし、逆に相手がどんなに多数派で、どんなに強大な権力を握っていても、道理の通らない、変てこなことを言い出したらやっつける、徹底的に立ち向わないといけない、ってことでしょ。せっかく宗教を扱っているのに、『息衝く』にそういう「法」や「天」の促し、人間を動かす起動力を感じとれなかった。もちろん、それが登場人物になくてもいい。いいんだけど、ないなら「ない」ということ、その欠落自体を明確に示す、批評的光景ってものが必要だと思うんです。
もっと具体的に言えばね。この映画では、何より森山の造型がとても頼りない。国会議員としての活動、議会内闘争に絶望したと称して、失踪や隠遁以外に選択肢がなくなるなんて……そんなことは、その人が「依法不依人」の原理を生きていたらありえない。むしろ、その時こそ本当の「運動」が始まる。養鶏業をやりながら、打算的な議会内闘争に左右されない、強力な大衆運動の基盤を作り続けるはずです。後で言うけど、武井(昭夫)さんのような「頑固な大衆運動主義者」の仕事と比べると、森山のあり方はとても浅薄に思えました。そういう所に想像が及ばない点、これは結局「実践」がわかっていない、わかった「ことにした」脚本サイドの、文学チックにこね上げたイメージになってしまっている。
同じことは、森山に変な着ぐるみを着せて滑稽化した演出にも言えます。もちろん森山は滑稽だし、それは絶対保証しますよ(笑)。でもその理由は、「カリスマに見捨てられたかわいそうな僕達」という問題設定におちこんで、結局自分達も「法」の原則をつかめない、主人公達の頼りなさが滑稽なのと同じはずです。この師弟はどっちもどっちですね。だから、森山には着ぐるみを着せるが、主人公達には着せない。彼らの方だけ、深刻な外見のままでいられるというのは、主人公側の怨恨を追認している……「追認」じゃないか。脚本自体が「法」にも「天」にも興味がなくて、ただもう「カリスマに見捨てられた僕達」を正当化したいんだな、と思ってしまいました。でも、それでよかったのか。森山や、則夫や大和達が本当にやるべきだったのは、堕落した「種子の会」を、内側から「法」によって変えることだったわけでしょう。
もちろん、浅薄なカリスマとそれへの個人崇拝、という事態は、現実の新興宗教全てで繰り返されています。公明党でも、オウムや幸福の科学でも。でも僕が言いたいのは、宗教の核心をつかんだ所で生じる、こうした事態への批評感覚の有無。それが映像にあるかないか、ということです。ちょっと補足すると、この感覚は決して「孤独に闘う」、ということではないから。それだと、また文学チックなイメージのこね上げになります。いや、客観的にも四面楚歌が続くんだけどさ(笑)、何というかな。直接的で感覚的な人間関係……カリスマだとか、自分の家族や血縁関係、お友達関係を特別扱いする、というあり方を一度断ち切ることで、それ以上の目に見えない価値を尊重することで、かえって人間と人間が普遍的に連帯できる。そういう主体的条件を生みだすことができる、と思うんです。だから、「孤独に闘う」という形容だと、その肝心の部分が消えてしまう。
たとえば、山﨑樹一郎さんが「一揆」の映画(『新しき民』)を撮っているでしょ。でも正直、僕は江戸時代になってからの、個別的で散発的な一揆にあまり興味がない。同じ一揆でも「思想」の差異が問題で、この点では江戸時代以前の「一向一揆」に関心があります。なぜかと言うと、あれだって結局孤軍奮闘だったかもしれないけどね。少くとも理念として、藩だの村だのという、地域的な狭隘さを乗り越える広がりを持っていた。門徒……一向宗の信者でさえあれば、どこに住んでいようが応援するという連帯の精神、広範な普遍性を原則上は持っていたし、ある程度それを実現していたからです。長々話したけど、『息衝く』の宗教に足りないな、抜けているな、と思った光景はそんな感じですね。」
木村 文洋
「仰ることで言えば、〝人〞に依ってしまっている主人公3人ではある、と思います。
確かに主人公たちは20代、森山に自分の能力を捧げたり、依拠することでの時間を過ごしてきました。それは〝人〞に依るということでしょう。慈だけは信仰―父の〝法〞に傷つけられた少女時代があり、彼女は早めに信仰を捨てています。
〝人〞に依らずに自分たちなりの模索をしていようとしている時間は、30代を越えた大和には色濃くあり―〝法〞に依って、ということは、彼だけは考えてもがいていると思います。ただ、彼にとっての〝法〞というのも模索中のものです。則夫にとっては残念ながらそうではなかった。則夫は〝法〞ではなく〝人〞に依るのが自分だった、ということに最後に気付き、大和に告げます。その3人の違いが、僕は大事だと思っているんです。
みなが皆、〝法〞に依る、ということは選べない。〝法〞の選び方もまだ探していくと思います。生まれた時から〝法〞に依ることが決まっていることに悩んでいる人もいるし、〝法〞というものが現在では、団体の利にすり替えられたりもします。投票活動、という卑近なことだけではないですよ。ただ、生まれたときからの団体に所属しながら、釈迦が何をしようとしていたかを考えるひともいる、個人個人で差異が生まれることが、いまは大事だと思ってこの映画をつくりました。」
鎌田 哲哉
「木村さんの考え、よくわかりました。では同じ問題を、別の観点から考えてみましょう。もっともらしく話してきたけど、僕は子供の時、この世に神も仏もない、神は俺だ、とか言っていた。だから、本当は宗教に興味はないです(笑)。問題は、やはり「政治」にある。つまり……ある主体が、宗教上の独立を徹底化する時がある。世俗的な、政治権力の価値体系から自分の信仰を分離して、その宗教的価値を純化し、自立させようとする。でも歴史的には、いわゆる政治の側が決してそれを許さない。宗教者が争いを求めていなくても、俗権の方でその自立を逃さず、圧迫や弾圧を加える状況が繰り返される。その時に、宗教者の言動も逆境でとぎすまされるというか、自分を貫く限り、ある根源的な「政治性」を帯びざるを得なくなる。既成の価値体系、僕達が日頃当然だと思っている価値体系を、根本的にくつがえす政治的原則を表現することになる。この点、ルターでも法然でも、また日蓮がどれだけ法然を罵倒していても、彼らの「政治性」の核心は共通している。そこから見る時、『息衝く』の政治性、その政治運動の射程をどう批評すべきか。そういう問題があると思います。
森山は有力な国会議員だったけど、種子党が「自衛隊のイラク派兵」に加担したことが原因で、十年前に失踪した。この設定にはさっき触れました。でも正確には、車中で回想する場面で、慈が一言だけ、(森山がいなくなったのは、皆が自分に依存してしまうからだ)という意味のことを言っている。本当はここに、「依法不依人」の原則が出現しかけている、と思います。それを徹底化したら、脚本が大幅に変る位の認識ですが、どうもそれが映画全体に浸透していない。そう感じたのは……主人公達が森山にとり残された「十年」があるわけでしょう。その「十年」を則夫や、特に大和がどうすごしたかが決定的な鍵になるのに、それが厚みのある時間性に思えなかったからです。
大和達は、森山を失って苦しんだでしょう。手ひどい打撃を受けたと思います。まだ若いから、森山をカリスマとして崇拝したのも仕方ないかもしれない。いや、俺は今日すごく甘いけどね(笑)……レーニンだって、若い時にプレハーノフと大喧嘩した時はそんな感じだった。でも、そこに「十年」という時間があれば、大和や則夫が態度変更を迫られる機会は何度もあったはずです。自分達がこだわっている原則や真理は、別に森山がいようがいまいが関係ないんだ、「人」にとらわれず推し進めないといけない性質のものなんだ、って。彼らが直接的な人間関係への依存を断ち切って、それと引き換えに世界中の人々と協力し、広く連合しあえる政治的言説を展開する。少くともそれへの変革を始めるのに、「十年」は十分な時間だと思う。それなのに、大和も則夫も十年前と同じ選挙運動に巻きこまれる、というより主体的にそのやり方に戻っちゃう。一日に何票とったとか、何軒家を回ったとか……森山から自立する、森山が落ちこんだ愚かなまちがいを克服するんじゃなくて、ただそれを繰り返す、模倣する方向に行ってしまう。何でそうなるかな、と思ったんです。
僕がそれを残念に思った理由は、この誤謬が何より、「選挙中心主義」にかかわるからです。僕達はすでに、心の中では選挙中心主義、つまり議会内闘争の絶対化にうんざりしているけど、少しもその状況を変えられていない。小泉だの小沢だの、安倍だの橋下だのと、どいつもこいつも選挙のことばかり。それで一時的に議席が得られても、社会構造全体を変革できるわけがないんだから。でも、これはとても根が深い問題です。武井さんなんか、もう1960年代からじゃないかな。日本共産党の選挙中心主義について、大衆運動をそれ自体として生かそうとも、強めようともしていない。ひたすら選挙の「手段」に、都合よく動員に利用することしか考えていない、って批評してる。共産党は実際にそのやり方で、衆議院の議席数をある程度増やしていますが、そういう目先の「勝利」が、実際には何を損い、その基盤にある何を傷つけているのかを、ずっと指摘し警告しているんです。でもさらにさかのぼると、それはローザ・ルクセンブルクが大衆ストライキ論争の時に、カウツキーの選挙中心主義について、ほぼ単独で言っていたことなんですね。
選挙がどうでもいい、と言っているわけではない。むしろ逆、究極的には選挙にも勝たないといけないけど、その勝ち方が問題です。いわゆる集票マシーン、企業や組合や宗教団体に頼って、その執行部の顔色ばかりうかがうとか、あるいは誰かの、その場限りの人気を当てにする、とかいうのはだめなんだ。それらをくつがえすために、政党が選挙の時だけ動員をかけるというのと違う、大衆運動そのものの創造が必要になってくる。決して選挙に直結したり、回収されたりしない、僕達が「下から」変っていく、批評的でインターナショナルな「人民」になっていく運動を強くしないといけない。おそらく、武井さんもルクセンブルクもまず「実践」がある、と思ってた。僕達一人一人が何かをやってみる、実際にぶつかっていくその経験だけが、今までの先入観を訂正したり、新しい作戦を思い付かせたりして、僕達に創造的な力を与えてくれる。そう確信していたと思います。対象の変革を通じて自己自身が変っていく、というのはそういうことで……木村さん、前に武井さんの遺著(『創造としての革命』)を書評されていたでしょう。あれに60年代のサークル誌の問題点が書かれてて、批評運動も創造運動も全く足りないじゃないか、って散々指摘されているのも、共産党の選挙中心主義に対する批判と並行してるはずです。
ただ、こういう「頑固な大衆運動主義」を貫くには、一つ時間的条件が必要だと思う。要するに、「選挙中心主義」を拒否するんだから、すぐには結果が出ない。ものすごく長い時間がかかって、やっている僕達自身が途中で死んじゃう、ってことです(笑)。目先の結果だけが結果だ、と勘違いしてる、頼りない連中にこれはできない。大西(巨人)さんの言葉で言えば、五百年たたないと物事は変らない。そういう時間感覚が「実践」の前提になってくる。でも、ルクセンブルクは最初からそう考えていた、と僕は思う。彼女のマルクスの引用には特徴があるんです。マルクスの若い時の、景気よくはったりを言ってる個所には全然触れない。そうじゃなくて、二月革命で負けて以後の、革命のヴィジョンについて根本的な断絶、自己批評を迫られた頃の……マルクスはその時、革命運動は砂漠を超えるユダヤ人のようなもので、今がんばっている人は、後世に果実を与えるために滅びないといけない、とか言っている(『フランスにおける階級闘争』)。ローザは主に、そういう個所に注目して批評を書いているんですね。
だから『息衝く』の場合、まず森山の設定自体が「選挙中心主義」と、それにしくじった後の隠遁を含めて滑稽ですが、則夫や大和達も全然そこからまぬがれていない。宗教的レベルで「法」の原理性をつかめていないのと同じように、政治的レベルでも「砂漠をこえる時間性」、そういう感覚を誰一人発見できていないと思います。だから最後に森山を訪問する場面……あれは森山だけじゃなくてね。主人公三人の方も着ぐるみを着て、全員鶏の格好でやり合ったらいい、と僕は思った。それはどうでもいいですが、この師弟の全体を相対化し滑稽化する「批評」を、少なくとも映画自体は持つべきだ、と感じたんです。」
木村 文洋
「選挙活動への埋没についてのお話でしたが、日本では多党制が成立せず、数十年、一党独裁であることが当たり前になっている、2011年を境にその負債に直面せざるを得なくなった、と思っています。その裂け目を、映画の中心には描いたつもりではいます。
そうであるならば、それを変えることに〝私〞を忘れる時間というのは軽視できることではない。ただ鎌田さんが仰る、その中で自身が変わっていくことが大事でしょう。それはこの映画のわずかな時間でも、則夫と大和の〝私〞というものはかすかにでも、変わっていると思うんです。平間という彼らの周辺の人間も巻き込んで…そのわずかな変化というものを描いたつもりでした。ただそれが、〝法〞に依る彼ら独自の大衆運動、ということまでに至っていたか、それを想像させる映画になっていたかは、仰るとおりかもしれません。十年の活動の重みが見えない、ということは重みあるご批判でした。」
鎌田 哲哉
「時間も迫ってきたので、あと二つ順不同で話します。まず、今言われた平間さんについて。杉田(俊介、『息衝く』共同脚本)さんがパンフレットで、平間さんを「『明暗』の小林や『カラマーゾフの兄弟』のスメルジャコフと同類」だと言っていますが、僕には疑問です。『明暗』を例にとると、終り近く、小林が主人公の津田に金をもらう場面がありますね。小林はその時、津田から自分に流れてきた「余裕」は津田には戻らない、もっと「余裕」のない人の方に行くだけだ、と言って、実際にその金を津田の目の前で、芸術家なのか社会主義者なのか、よくわからない貧乏な青年に即座に渡してしまう。それで津田は、もちろん激しい憎悪にとらわれるんだけど、同時に自分のあり方……中産階級的な生存では想像もできないひび割れ、地底をのぞきこまされる。津田にとって、意識の上でどう考えようと、小林の実践自体が「世界」への抜け穴になっているわけです。
他方、平間さんの場合はどうか。途中で則夫に因縁をつける場面は面白く、僕も期待して見ていましたが、則夫が平間さんを通じて、自分の気付かなかった「世界」に脅かされる、という光景は生じていない。『明暗』とは逆に、平間さんの方が則夫の世界に巻きこまれるというか……そもそも則夫は平間さんのことが好きで、ずっと声をかけ続けていますが、平間さんの方でも、最後に九州の父親の元に戻ることで、則夫がこだわる「家族」のつながりを受けいれていく。平間さんが「ホームレスと日雇い労働者の間を揺れ動く」というだけで、『明暗』の小林と「同類の地底的な声」だということはなく、それぞれが主人公に何をもたらすか。その差異を見ないと、まっとうな「批評」にならないんじゃないかな。
もう一つは、「カリスマ」の把握についてです。今日の最初に、「「人」への依存はあっても「法」への緊張がない」と言ったけど、正確に言うと、そもそもカリスマの扱い方自体に限界というか、とんねるずの石橋何とかが言うのと変らない、通俗的な発想を感じたんです。
元々、「カリスマ」とか「カリスマ的支配」という言葉は、マックス・ウェーバーが使って有名になったものですね。でも、彼の論文を実際に読むとわかるけど、ウェーバーが本当に追跡しているのは、カリスマが超人的な影響力を行使しました、という単純な話ではない。むしろ、そのカリスマが日常化し、主に血統や世襲によって継承され、変質していく過程が分析の主題なんです。ものすごく偉大なカリスマがいたって、それだけに頼っていたら、いかなる集団も組織も持ちこたえられない。その人が死んだら、存続できなくなる。そこに後継者の問題が生じて、だから「世襲カリスマ」や「血統カリスマ」が発生してくるわけです。この場合、特定の個人が持つ神秘性とか、超人的な能力はもはやいらない。万世一系とか、代々の子孫とか言うだけで、どんな馬鹿でも指導的地位に付けるから、「カリスマの日常化」が生じるんですが、だからと言って「法」や「天」の普遍性は相変らず実現されていない。
つまり……僕達は「カリスマ」と言えば、扱いやすい、わかりやすい森山タイプの個人を想定しますね。そこから大げさで、深刻な確執のドラマまで作ってしまう。でもその時、より本質的な問題、「世襲カリスマ」や「血統カリスマ」の問題から無意識に逃げていないでしょうか。今の世の中が、二世、三世で腐り切っているのはともかく、日本における最大の「世襲カリスマ」は天皇制です。憲法だって、「法」や「天」の原則を徹底化すべき所、いまだに第一章の天皇条項だけが、飛び地のようにそれを阻止している。「カリスマ」を特定の個人に矮小化する発想は、そういう状況に対して発言したり、介入できない脚本サイドの臆病さの表現じゃないかな。仮に『息衝く』が森山でなく、「種子の会」にも生じているはずの、「世襲カリスマ」の問題を扱ったとしますよ。その方がずっと状況介入的だし、少くとも俗っぽくはなかった、と思うんです。」
(以下、会場全体でお客様との討論が続くが省略)
木村 文洋
「鎌田哲哉さん、今日はありがとうございました。最後に私の方から一つ、前提に戻りたいことがあります。私の尊敬している映画監督で、映画づくりとは、ひとに電話をまずかけることだ、と言った映画監督がいます。私は10代、ひとに電話をかけることができませんでした。ひとの時間を一日、いや半日でももらうことが自分には出来ないと思っていました。私は17歳の頃に好きだった映画、というものをつくりたい、という経過を通して、初めて映画を撮る20歳までに〝ともだち〞に出逢う、という願望を叶えたのだと思います。ともだち、とは迷惑をかけることを恐れないひとのこと。かけた迷惑の代償、責任を、自分も負える、という覚悟と責任とを引き受けること。そして出来得るならば、その迷惑のかけ合いによって、お互いが知り得ない地平が切り拓かれ、そこに不特定多数のひとが歩いていくことが、これまでの理想でした。26歳の頃に六ヶ所村を初めて観て、スタッフでその光景や問題に対しての思いを共有していったことも『息衝く』には反映されていますが、鎌田さん仰られるとおり、私の信仰や映画づくりへの認識は、〝人に依る〞という最初の認識が強かったように思います。そして本日、お客様とお話していても、そもそも10代、私に信仰を教えてくれた友人は、本尊を祈りながらも誰か特定の対象を祈るのではない、まず自身を変革させていくのだ、と教えてくれたことを何より強く思い出しました。観ている光景が変容する奇蹟ではなく、光景を見つめる人間の心を変えていくことを、それによって〝ただ、ひとつの言葉〞から変えていくことを、教えてくれたのだと思います。」
鎌田 哲哉
「木村さんが今言われた、「ひと」や「ともだち」との結びつき……それは本来、カリスマだのお友達だのの関係とは違う、「お互いが知り得ない地平」=「法」や「天」に開かれた共同作業のことじゃないかな。でも、この話はもうやめますね(笑)。その代り、こちらも最後に一言言います。
『息衝く』の主要な舞台は田無タワーの周辺ですが、予告編を見た時から、僕はそのことに驚いていました。まだ20代の頃かな。僕自身がこのタワーのすぐ近所で働いていたからです。しかも、時期もほぼ同じ……則夫と母親が東京にやってくる場面で、工事中の看板に「平成元年」とあったんですが、僕の方はその次の年。ちょうどバブルがはじけた90年のことで、田無タワーも完成直後だったはずです。
僕はその頃、西武新宿線の「花小金井」という駅の近くで、小さな塾を経営していました。経営というか、バイト先の塾長が新年度の直前に、半分夜逃げみたいに塾をやめてね(笑)。僕達講師も、生徒も皆困ってしまって、仕方なく一年だけの約束で、代りに責任者をやったんです。塾の場所自体は小平市内ですが、ちょっと歩くと田無市(現西東京市)で……田無タワーの所在地は、「芝久保町」と言うんでしょう。小学校高学年から高校生まで、そこからも結構生徒が通っていて、試験対策とかも大変で、今でも地名を覚えています。
つまり、木村さんが北側から、東久留米の方から見続けていたあのタワーを、当時の僕は南から、改札前の階段を降りる度に一瞥して、毎日職場に通っていた。もちろん、周囲の風景はすっかり変っています。昨日、小平市近くの安ホテルに泊まって、今朝久しぶりに花小金井を歩いてきたけど、駅や周辺の区画に昔の面影はなかった。そもそも高いビルやマンションばかりで、駅から田無タワーなんか見えません。でも、それでかえって感傷的になりました。あの時教えていた田無の生徒の中に、主人公の友達がいた……もしかして、則夫や大和や慈本人がいたかもしれない。そういう空想にとらわれていました。
だから今回、『息衝く』を批評するのは大変苦しかったです。ごく親しい、若い友人が全力をつくした作品に、致命的な認識上の「傷」を感じて、それを公開の場で言うのが辛かった、というだけではありません。木村さんの映像の強度が僕をつかまえて、自分では対象化しにくい、よちよち歩きのなつかしい時代にさらって行ったからです。でも、それと「批評」は違う。「批評」はやはり、「感傷」や「被害者意識」に溺れることでないと思う。「超人的なカリスマに見捨てられた主人公」と言う設定……個人的に話した限り、それは杉田さんとか、誰とかに影響されたわけではない。木村さん自身が、あくまで自分の判断で選んだ発想のようですね。でもそういう問題設定、無意識に陥っている甘えた被害者面によって、僕達は何に目をそむけ、どんな問題から逃げているのか。「依法不依人」の原則なのか、「砂漠をこえる時間性」なのか、「世襲カリスマ」の暴力か、それとも別の何かなのか。木村さんの新しい「実践」が、これらの疑問に立ち向う作品であってくれたら、僕は大変うれしいです。」
(2018年4月21日(土)下北沢トリウッドにて)
かまだ・てつや 1963年北海道松前町生まれ。
最近の批評文に、「木村文洋のりんご」(『息衝く』パンフレット)
「憤ることと物のあはれを知ること」など。